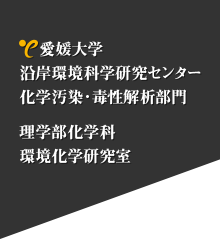平成23年度-研究実績
POPs候補物質の代替品(BTBPE:トリブロモフェノキシエタン、DBDPE:デカブロモジフェニルエタン、DP:デクロレンプラスなどの臭素系難 燃剤)の他、消費量が増加している有機リン系難燃剤(リン酸エステル類)についてLC-MS/MS、GC-MSによる分析法を開発し、イガイや堆積物など の生物環境試料の分析を試みたところ、BTBPEの汚染はアジア地域では未だ進行していないこと、DBDPEは途上国に比べ先進国で汚染レベルが高いこ と、DPを含めこれら代替難燃剤汚染の歴史トレンドは近年上昇傾向にあること等が判明した。また、リン酸エステル類を途上国のヒト母乳から初めて検出し た。ベトナムe-waste処理地域の住民から採取した血液・母乳試料を分析したところ、母乳から臭素化ダイオキシン類が検出され、e-wasteの不適 正処理がその曝露要因となっていることを指摘した。また、血中のバイオマーカーと有害物質濃度の相関解析から、鉛曝露によるヘモグロビンの代謝異常や PCBsによる甲状腺ホルモンのかく乱などが示唆された。カズハゴンドウなどの海棲哺乳動物の血液・肝臓・脳試料等を対象に、PCBs・PBDEsおよび その水酸化代謝物であるOH-PCBs・OH-PBDEsやメトキシ化PBDEs(MeO-PBDEs)を測定し、その体内分布や代謝動態、起源等につい て解析したところ、OH-PCBs・OH-PBDEsが脳に移行すること、鯨類に蓄積するOH-PBDEsの大半は、人為起源のPBDEs代謝物よりも自 然起源のMeO-PBDEsに由来することが示唆された。野生高等生物の抽出液を化学分画し、p,p’-DDEおよび有機スズ化合物が抗アンドロゲン受容 体活性物質であることを同定した。難分解性有機汚染物質とconstitutive androstane receptorの結合アッセイ系を構築し、ポリ臭素化ジフェニルエーテルがハイリスク物質であることを明らかにした。また、水酸化PCBsの暴露による 神経形成異常は甲状腺ホルモンの機能かく乱に起因しないことが示唆された。